
アスリートのキャリアとは何か?競技人生のその先を考える
はじめに
アスリートのキャリアは、他の職業と比べて非常に特異です。ピークの年齢が若く、引退も早い傾向があり、その後の人生設計が大きな課題となります。本記事では、アスリートのキャリアの全体像を概論的に解説し、現役時代から引退後のセカンドキャリアに至るまでの流れや課題、支援の取り組みについて考察します。
1. アスリートキャリアの特徴
-
短命なキャリア:競技によりますが、20代〜30代前半で引退するケースが多い。
-
早期専門化:10代から競技に集中することで、他の分野での経験が不足しがち。
-
身体的・精神的負担:肉体の酷使だけでなく、勝敗によるメンタル面の影響も大きい。
-
社会的評価の変化:現役時代の注目度が高いため、引退後のギャップを感じることも多い。
2. キャリア形成のフェーズ
-
準備期(ジュニア期)
技術習得と基礎体力づくり。将来のトップアスリートとしての土台を築く時期。 -
達成期(競技者としてのピーク)
目標達成や勝利を追い求める時期。パフォーマンス向上とともにスポンサー・メディア対応も重要に。 -
移行期(引退前後)
パフォーマンスの低下とともに、キャリアの転換点。心理的ストレスが最も高まる時期。 -
再定義期(セカンドキャリア)
指導者、解説者、ビジネス、教育など、新たなアイデンティティを模索し再構築する時期。
3. セカンドキャリアの課題と現状
-
進路の不透明さ
競技以外の進路が見えづらく、迷いが生じやすい。 -
スキルのギャップ
社会で求められるスキルと自身の経験とのギャップがある場合、再教育が必要。 -
収入の減少
引退後に収入が激減するケースもあり、金銭的な不安を抱える人も。 -
精神的喪失感
「現役アスリート」という肩書きを失うことで、自己喪失を感じる場合がある。
4. 支援制度と取り組み
-
キャリアサポートセンターの設置
JOCや各競技団体が行うカウンセリング・研修プログラム。 -
教育機関との連携
大学進学や資格取得の支援。 -
企業とのマッチング
スポーツ経験を活かせる職場とのマッチング支援やインターン制度の活用。
アスリートのセカンドキャリア事例
1. Aさん【女子バレーボール選手 → 医療福祉業界へ】
大学卒業後、Vリーグの実業団チームで5年間プレーしていたAさんは、引退後にリハビリ施設の理学療法士として再スタート。競技人生の中で怪我や治療に向き合った経験から、医療職に関心を持ち、現役時代から通信教育で資格取得を目指していました。
📝 ポイント:
-
現役中からの資格取得準備
-
競技経験が新しい職業での信頼に
「人を支える」視点でのキャリアチェンジ
インタビュー企画:「女子バレーボール選手引退後のリアル」
― 現役を終えたアスリートたちは今、何をしているのか?
Aさん(30代前半/元Vリーグ選手・現:理学療法士)
「現役時代、何度もケガをして、理学療法士の方に本当にお世話になったんです。自分も“支える側”になりたいと思ったのが、きっかけでした。」
5年間、Vリーグの実業団チームでプレーしたAさん。
20代後半で引退を決意し、その直後から専門学校に通い始めました。
「理学療法士の資格って、簡単じゃないんですよね。でも、現役中から少しずつ通信講座で勉強していたので、スムーズに切り替えられました。」
現在は整形外科のクリニックに勤務しながら、時々ジュニア選手のトレーニング指導も行っているそうです。
「“プレーする自分”を終えても、“支える自分”として、スポーツと関われているのが嬉しいです。」
2. Bさん【陸上短距離選手 → 中学校の教員へ】
Bさんは大学まで陸上の短距離で活躍し、実業団にも所属していましたが、競技成績に限界を感じて引退。その後は中学校の保健体育教員として働きながら陸上部の顧問を担当。自分の経験を次世代の子どもたちに還元し、教え子が大会で入賞することが新たなモチベーションになっています。
📝 ポイント:
-
-
自身の競技経験を教育に活かす
-
教職課程を学生時代に履修していた点が転身の鍵
-
現場でのやりがいと競技との繋がりの維持
-
インタビュー企画:「陸上短距離選手引退後のリアル」
― 現役を終えたアスリートたちは今、何をしているのか?
Bさん(30代/元実業団アスリート・現:中学校教員)
「競技者としては目立つ存在じゃなかったけど、教えるのが好きだったので、教職を目指していました。」
大学では教育学部に所属しつつ、実業団でも短距離走を続けていたBさん。
28歳で引退後、すぐに教員採用試験に挑戦し、現在は中学校で保健体育を教えています。
「引退後すぐは“競技してない自分って何なんだろう”って思ったこともありました。でも教え子の成長を見ていると、自分の経験が確かに役立ってるって実感します。」
顧問を務める陸上部では、生徒たちから「走り方が的確すぎる!」と尊敬を集める存在に。
「スポーツって“勝つこと”だけじゃない。自分にとっては、今も“伝えることで競技と関われる”のが一番の喜びです。」
3. Cさん【男子体操選手 → 一般企業の営業職へ】
Cさんは大学卒業後、社会人クラブチームで体操競技を続けながら就職活動を進め、スポーツ用品メーカーの営業職として入社。競技経験を活かした商品説明が顧客からの信頼につながり、営業成績も好調。競技とは異なる形でスポーツと関わり続けられる職場環境が、本人の満足感にもつながっています。
📝 ポイント:
-
アスリートとしての経験が「営業の説得力」になる
-
現役引退後もスポーツとの関わりを持てる職場選び
-
周囲のサポート(家族・先輩・企業)が転身の支えに
インタビュー企画:「男子体操選手引退後のリアル」
― 現役を終えたアスリートたちは今、何をしているのか?
Cさん(20代後半/元社会人クラブ体操選手・現:スポーツ用品メーカー営業)
「就職=競技の終わり、って思ってたけど、働く中で“スポーツとの新しい関わり方”があるって気づきました。」
大学で体操を続け、卒業後は社会人クラブに所属しながら就職活動をしていたCさん。
現在はスポーツ用品メーカーで営業職として活躍中。
「お客様の前で、“僕も体操やってました”って言うと、やっぱり信頼感が違うんですよ。商品への説得力が出るっていうか。」
競技者時代の経験が、ビジネスの現場でも活きているという手応えを感じています。
「競技を離れても、“好き”を活かせる仕事に就けたのは、自分なりに行動してきたからだと思います。周りに流されすぎず、“自分に合った道”を選ぶのが大事ですね。」
🎯 補足:トップアスリートではない人こそ「戦略的準備」がカギ
メディアに取り上げられることが少ないアスリートは、引退後に注目されにくい分、より戦略的なキャリア設計が重要になります。
中には、「スポーツ推薦で進学したものの、勉強との両立が難しかった」「競技に打ち込む中で、社会との接点が薄かった」といった悩みを持つ選手も多く、現役中からの情報収集・スキル習得・人脈形成が大きな差を生むとも言えます。
おわりに
アスリートのキャリアは「競技成績」だけではなく、その後の人生も含めて考えるべきものです。現役中から将来を見据えた準備を進めることで、より豊かな人生設計が可能になります。個人・団体・社会が一体となり、持続可能なアスリート人生を支える仕組みづくりが求められています。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。


の勘定科目-600x450.png)





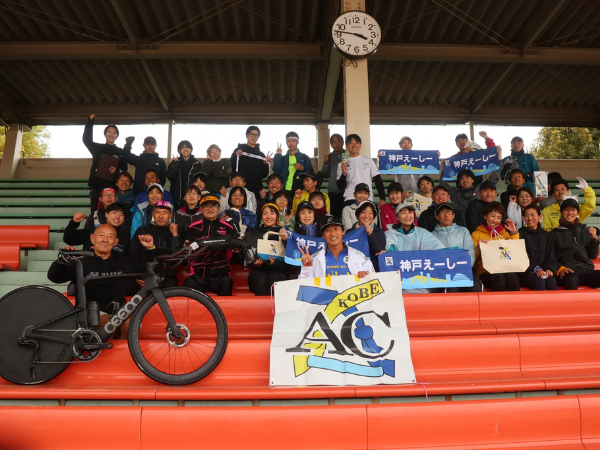







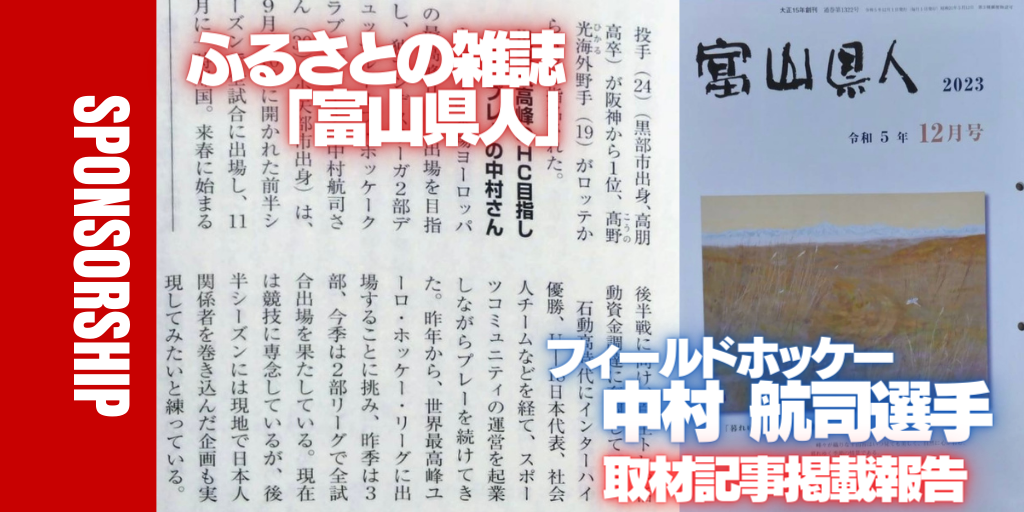













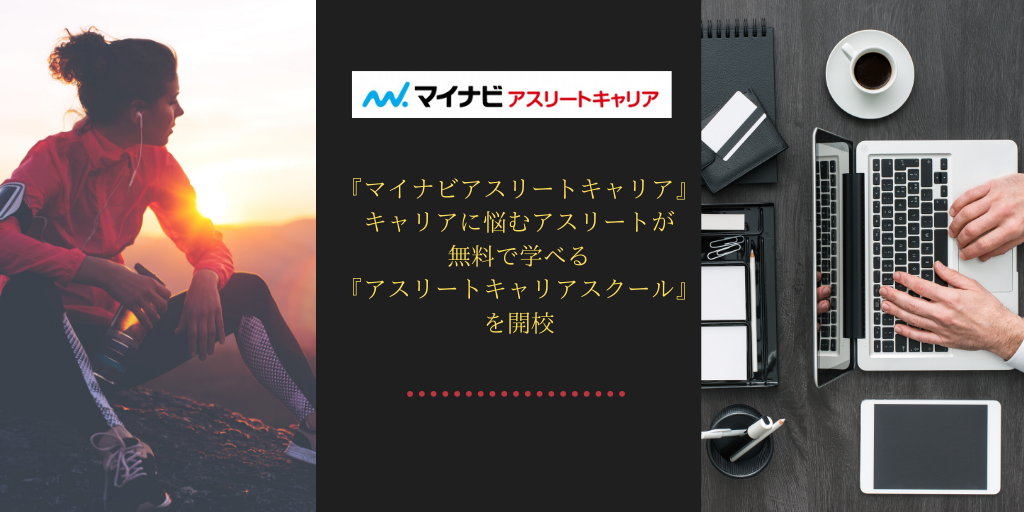






の募集開始-1.png)
この記事へのコメントはありません。