
日本一の実業団バドミントン部が明かす「感謝の心」が生む強さの秘密
企業スポーツの世界で頂点を目指す選手たちは、どのような環境で日々を過ごしているのでしょうか。仕事とスポーツの両立、そして「活動させていただいている」という感謝の心。日立情報通信エンジニアリング男子バドミントン部は、全日本実業団で初の日本一を達成した強豪チームです。
スポーツコミュニティ株式会社が運営するYouTubeチャンネル「アスキャリ」では、同チームの監督が、実業団スポーツの実態や指導哲学、そして日本バドミントン界の進化について詳しく語っています。この記事では、その貴重なインタビュー内容をもとに、トップレベルのバドミントンチームの強さの本質に迫ります。企業スポーツに興味がある方、バドミントン競技者、そしてスポーツビジネスに関心のある方にとって、多くの学びが得られる内容となっています。
仕事とバドミントンを両立する実業団の日常
実業団スポーツは、大学スポーツを終えた選手がオリンピックや世界選手権を目指す最後の場所です。この世界に入れるのは、ほんの一握りのトップアスリートに限られています。日立情報通信エンジニアリングのバドミントン部では、選手たちは仕事をしながらバドミントン活動を行っています。
1週間のスケジュールを見ると、その恵まれた環境が分かります。月曜日、水曜日、木曜日は午前中が勤務で、午後2時から6時までが練習時間となっています。火曜日と金曜日は、会社からの配慮により終日練習が許可されているのです。
実はこの環境は、バドミントン界においては非常に恵まれたものです。実業団チームの過半数は、定時までしっかり働いてから、仕事が終わった後にバドミントン活動をする体制をとっています。業務時間中に練習ができるチームは限られているため、選手たちはこの環境に深い感謝の念を持ちながら活動しているのです。

100%の出力を引き出す独自の練習メソッド
バドミントンは感覚的な側面も強いスポーツです。練習時間が長く、シャトルを打つ時間が多いほど上達すると考えられています。コートに入っている時間は、一人当たり大体10分から15分程度のスパンでメニューを交代しながら行います。2時間半ずっと入りっぱなしでは、体力的に相当厳しいためです。
監督が就任してから最も重視している名物練習がノックです。通常は20球程度のノックを行うところを、半分に減らして10球にしています。これは単なる手抜きではありません。1球1球をフルパワーでスマッシュなど早い球を打ち込む、出力を最大限に上げる練習として位置づけられているのです。
20球続けて行うと疲れが出て100%の出力が出せない状態になります。しかし試合で100%を出すためには、普段から100%を出す練習をすることが必要だという考えに基づいているのです。この練習法は、質を重視した効率的なトレーニングの好例といえるでしょう。
「活動させていただいている」意識が生む強さ
日立情報バドミントン部の最大のミッションであり、チームの根幹となる部分は「仕事とバドミントンの両立」です。これは、日頃から業務面で関わっている方々への恩返しをバドミントンを通じて伝えるという考えが背景にあります。
企業スポーツと大学スポーツの大きな違いは、意識の持ち方にあります。大学生までは自分たちでお金を払って活動していますが、企業ではサポートを受けられます。そのため「活動している」ではなく「活動させていただいている」という考え方のチェンジが非常に重要なのです。
この意識は、感謝の気持ちが薄れてしまうことを防ぐために必要であり、監督は新しく入社する選手に対し、マインドセットとして繰り返し伝え続けています。会社に対して、応援してくれている社員の方に対しての恩を重く置いて活動しているからこそ、チームは勝つことに貪欲になれているのです。
技術よりメンタルが勝敗を分ける理由
実業団レベルでは、技術よりもフィジカル、さらにフィジカルよりもメンタルの部分が最も大事だと監督は語ります。重要度の順番は、メンタル、フィジカル、技術の順です。
バドミントンは激しいスポーツであり、体が動かなければ生きた球が打てなくなるため、フィジカルの強さは非常に重要です。しかし「技術だけ機械値でも日本一のてっぺんは取れない」状態だといいます。
対人スポーツであるバドミントンでは、「相手に負けたくない」「ここ1点を失いたくない」という思いから、いつものプレーができなくなったり、弱気になってしまうことがあります。これがメンタルの課題として表れるのです。バドミントンは流れのスポーツでもあり、精神面のコントロールが勝敗を大きく左右します。

頭脳プレーと戦略が勝利を呼ぶ
バドミントンは早い弾のやり取りに見えますが、実は頭脳プレーがあるスポーツです。次の2球、3球の先を読んで配球をする戦略が持てているかが重要になります。
ダブルスにおいては、パートナーとのコンビネーションや、どのような配球をするかという戦略の事前準備が、勝つために必要不可欠な要素です。具体的には、相手にとって打ちにくいところにシャトルを出し、相手の返球コースを制限させた上で、次の球をしっかり潰しに行くという戦略が用いられます。
21点ゲームの最初の11点ぐらいまでは、お互いの配球や癖の読み合いから入り、徐々に相手の癖を掴んで崩していくというゲームメイクが行われます。監督やコーチも、選手と同じように相手の癖をずっと見ているのです。
興味深いのは「ちょっと変な意味ですと、性格悪い人勝つ」という表現です。これは、相手の嫌なところを突いて、徐々に体力を削っていく戦いだということを示しています。スポーツマンシップの範囲内で、いかに相手を心理的に追い込めるかが勝負の分かれ目となるのです。
感覚を研ぎ澄ます長年の積み重ね
一瞬のスポーツに見えるバドミントンですが、監督によれば選手はシャトルをあまり見ていないといいます。逆に感覚的なところが大きく、取られても前を見据えた状態で、この辺りで取っているという感覚があるため、瞬きをしても取れるとのことです。
これは「長く練習し、長くラケットを持って打っている」選手だからこその感覚です。何年も、何万回もシャトルを打ち続けることで、体に染み込んだ感覚が生まれます。この言葉は、諦めずに練習を続けることの大切さを示しているのです。
日本バドミントン界の進化とスカウティング戦略
かつてはインドネシアや中国に勝てない世界観でしたが、最近の日本はガチンコで戦えるようになっています。この変化の要因として、現在の世界トップで活躍する日本の選手は、小さい頃から、小学生や幼稚園ぐらいからバドミントンを続けている者が過半数を占めていることが挙げられます。
彼らはクラブチームや名門校を通ることでスキルを身につけ、さらに小さい時から世界を経験することで、日本国内では味わえないフィジカルの差やスキルアップを図ることができています。バドミントン協会も、現在では中学生や小学生の日本代表チームを編成し、育成に力を入れているのです。
日立情報が選手をスカウティングする際は、主に大学生の2年生・3年生にスポットを当て、成績やポテンシャルを見極めつつ、コーチ陣と話をしてスカウト計画を立てます。最近では高校生にも目を向けており、大学4年間を経由せずに実業団で4年間育てるという選択肢も増えています。
以下の表は、スカウティングの対象と特徴をまとめたものです。
| 対象 | メリット | 課題 |
|---|---|---|
| 大学2-3年生 | 成熟した技術と体力、実績が見える | 獲得競争が激しい |
| 高校卒業生 | 長期育成が可能、伸びしろが大きい | 体の強さに差がある(4年で補える) |
日立情報は全日本実業団で初の日本一を達成しました。そして今、11月末から始まるS/Jリーグでの初優勝、さらには連覇を目指しています。長期目標としては、2028年のロサンゼルスオリンピック出場を目指す選手をサポートすることを掲げています。
YouTubeチャンネル「アスキャリ」では、監督の言葉をさらに詳しく聞くことができます。具体的な練習メニューの詳細や、選手たちの日常、そしてオリンピックを目指す若手選手たちの姿など、この記事では紹介しきれなかった貴重な映像が満載です。企業スポーツの最前線で戦う選手たちの真剣な眼差しと、感謝の心を持ちながら勝利を目指す姿勢に、きっと心を動かされることでしょう。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



























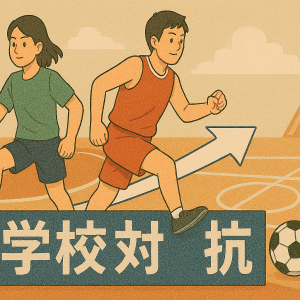

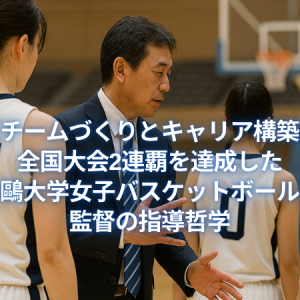
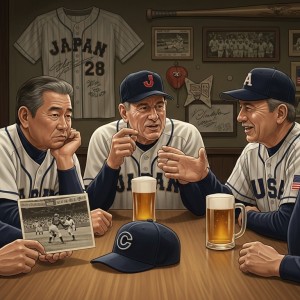
この記事へのコメントはありません。