
【日本一の監督が語る指導論】勝利より大切なものとは?東京五輪の舞台裏と学生を自走させる育成術
アスリートとして競技に打ち込んできた方々にとって、引退後のキャリアを考える際、最も参考になるのは「競技を通じて何を学び、どう社会で活かすか」という視点ではないでしょうか。
YouTubeチャンネル「アスリートキャリア」の後編では、日本大学柔道部の監督が、東京オリンピック強化本部長としての重圧、そして学生を「自走」させる指導論について赤裸々に語っています。この対談から見えてくるのは、勝利至上主義から脱却し、選手一人ひとりの人生を見据えた育成の重要性です。現役アスリートはもちろん、引退後のキャリア形成を考えている方、そしてアスリート採用を検討している企業の方々にとって、競技で培った力をビジネスでどう活かすかのヒントが詰まっています。
社会人チームと学生チーム、指導の違いから見えた本質
監督としてのキャリアは、社会人トップチームALSOKから始まりました。そこには意識も能力も高い一流選手が集まっており、監督の役割はマネジメントが中心でした。選手たちは自分がどこまで頑張るべきかを確立しており、放っておいても自分で進んでいける環境だったのです。
しかし、大学の柔道部では状況が一変しました。学生には道を提示したり、話を聞いてあげたりする必要があります。当初は「なぜ言ったことがわかってもらえないのだろう」「なぜ続けられないのだろう」という焦りや苛立ちを感じることも多かったといいます。トップ選手を見てきた監督にとって、このギャップを埋めるのには時間がかかりました。
しかし現在では、選手たちそれぞれに事情があり、できない理由ややる気がなくなってしまう理由があるという「逆の裏側」から見てあげる目が持てるようになったと語っています。完璧ではないものの、以前よりは角度を変えて選手を見るワンクッション、ツークッションを置けるようになったのです。この視点の変化こそが、指導者として成長した証といえるでしょう。
「勝っても負けても自分の柔道をしよう」という送り出し方
現役時代、27歳で全日本選手権に優勝した際は「何が何でも勝つんだ」という悲壮感の塊で臨んでいました。若い指導者だった頃も、その経験から「何が何でも勝つんだ」という思いを学生に伝え、気持ちを高揚させるようなペップトークで送り出していたといいます。
ところが最近のインカレで優勝した際には、あえて「必ず勝ってこい」という送り出し方をしませんでした。代わりに伝えたのは「勝っても負けても自分の柔道をしよう」という言葉です。学生が一番緊張し、一番勝ちたいと思っている状況で、普段やっていることを100%出させてあげることが最も大事だと考えるようになったからです。
優勝という結果は出ましたが、日大には今年ポイントゲッター(エース)がいませんでした。それでも全員が自分のやるべき仕事をしたことで力を出し切れたと評価しています。この指導姿勢の変化は、勝利という結果だけでなく、選手の成長プロセスを重視する姿勢の表れです。優勝自体を目標や目的にするのではなく、優勝はあくまで「指標」の一つであると位置づけています。真の目的は、柔道を通じて学生が成長し、自走して社会に出ていけること、そして社会に有益になることなのです。

東京オリンピック強化本部長という重圧
東京オリンピックのタイミングで、監督は山下先生からの依頼を受け、強化本部長に就任しました。世界選手権やオリンピックに出場経験のない自分が、歴代のスターの後の強化委員長を務めることに対して、当初は「青天の霹靂」であり「戸惑いと恐怖しかなかった」と明かしています。
東京オリンピックが地元開催であったため、4年間パリ五輪が終わるまで、「いつも胸の中に石が乗っかっているような」強烈なプレッシャーを感じていたといいます。日本柔道は毎回全員が金メダルを目指しているため、客観的に見て成功した内容ではあるものの、金メダルを取らせてあげたかったという思いや、悔し涙を流した選手への思いから、「もっとやれたことがあったのではないか」という反省の念を抱いています。
成功に結びついた要因として、監督は無観客開催を挙げています。選手たちは落ち着いて自分の状態を維持でき、マスコミの殺到や余計な情報が入ってこなかったため、試合に集中できたという意見が多く聞かれました。また、地元開催により移動のロスや時差がないことも、日本にとってやりやすい面でした。これらの要因は、アスリートのパフォーマンス発揮において、環境要因がいかに重要かを示す好例といえるでしょう。
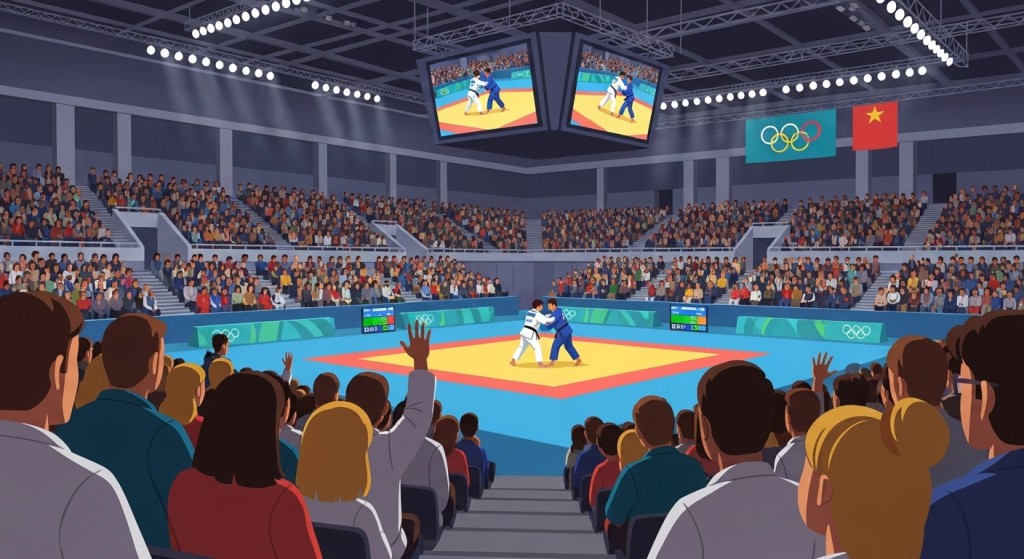
「伸びしろ」を見抜くスカウティングと長期的視点
日本大学柔道部の特徴は、寮があることで部員同士の付き合いが色濃くなり、「兄弟というか家族というか」のような雰囲気があることです。昔のような厳しい上下関係はほとんどなくなっており、これは日大だけでなく全柔道界的な傾向であると認識されています。
柔道人口が減る中で、選手の獲得競争は非常に激化しています。100名を超えるような柔道部は、中学校などから10年計画で選手を育成していることが多い状況です。日大では、いわゆるチャンピオンを早い段階でリクルートするのは難しいため、将来性や「伸びしろ」がある選手を、早い段階で見つけて声をかけていく「一本釣り」のようなスカウティングが特徴となっています。
見極めるポイントは身体能力や技術だけではありません。稽古を見て、しっかり自分で取り組めるかどうかという気持ちの面、そして既に非常にうまい選手よりも、まだ完成されていないが、ここを直せば良くなるのではないかという伸びしろを持つ選手を見つけようとしています。この視点は、企業がアスリートを採用する際にも参考になるでしょう。完成された能力よりも、成長可能性や自ら学ぶ姿勢を重視する採用戦略は、ビジネスの世界でも有効です。
監督は、結果が出なかった選手に対しても責任を感じており、選んできてくれた学生には感謝しています。大学スポーツの監督として、結果が出なかったとしても、選手として目が出なくても社会に出て成功する者もいるため、育成については「少し長い目で」見たいと考えています。この長期的な視点こそが、アスリートのセカンドキャリア支援において最も重要な考え方です。
YouTubeチャンネル「アスリートキャリア」で全編を視聴しよう
この対談では、監督の指導哲学の変遷、東京オリンピックでの舞台裏、そして学生を自走させる育成術について深く掘り下げられています。動画では、監督が実際にどのように選手と向き合い、どんな言葉をかけているのか、そしてアスリートが社会で活躍するために必要な力とは何かについて、さらに詳しく語られています。
ぜひチャンネル登録をして、アスリートキャリアの可能性を一緒に探っていきましょう。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



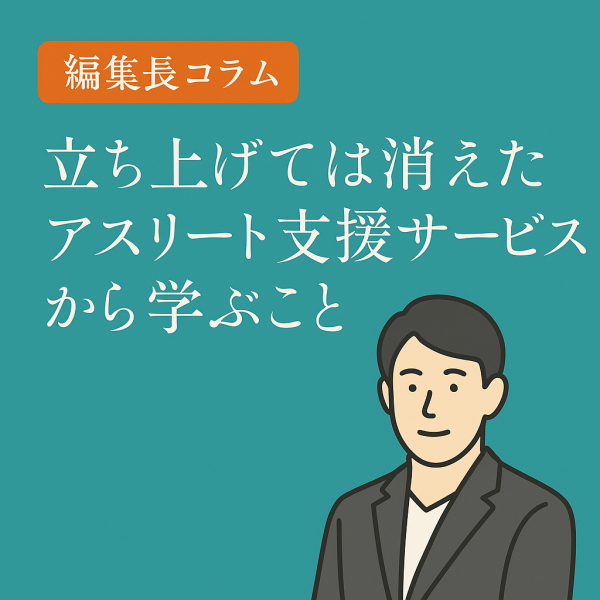
の勘定科目-600x450.png)











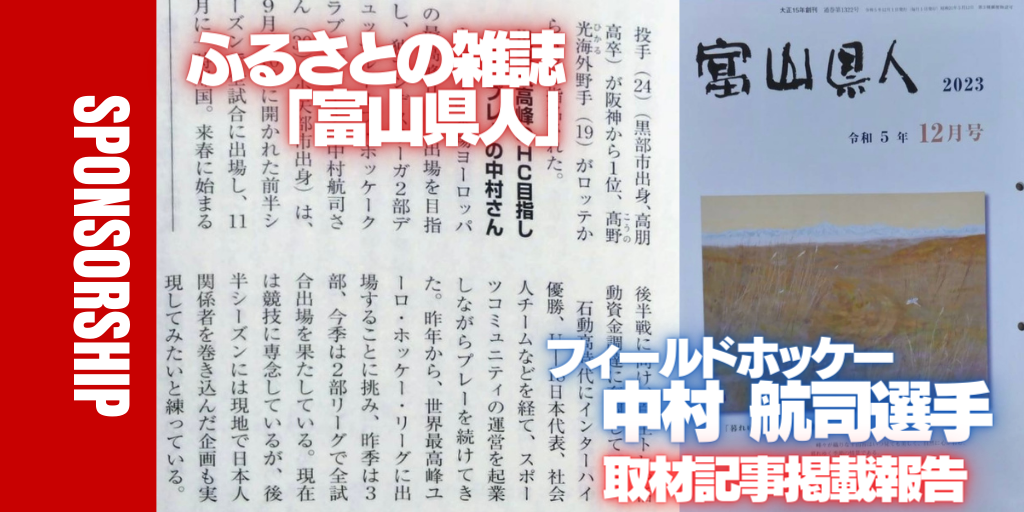



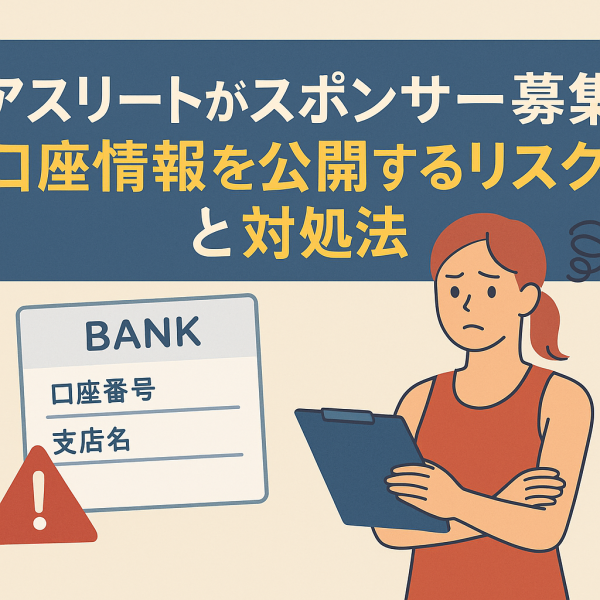










』始動.png)

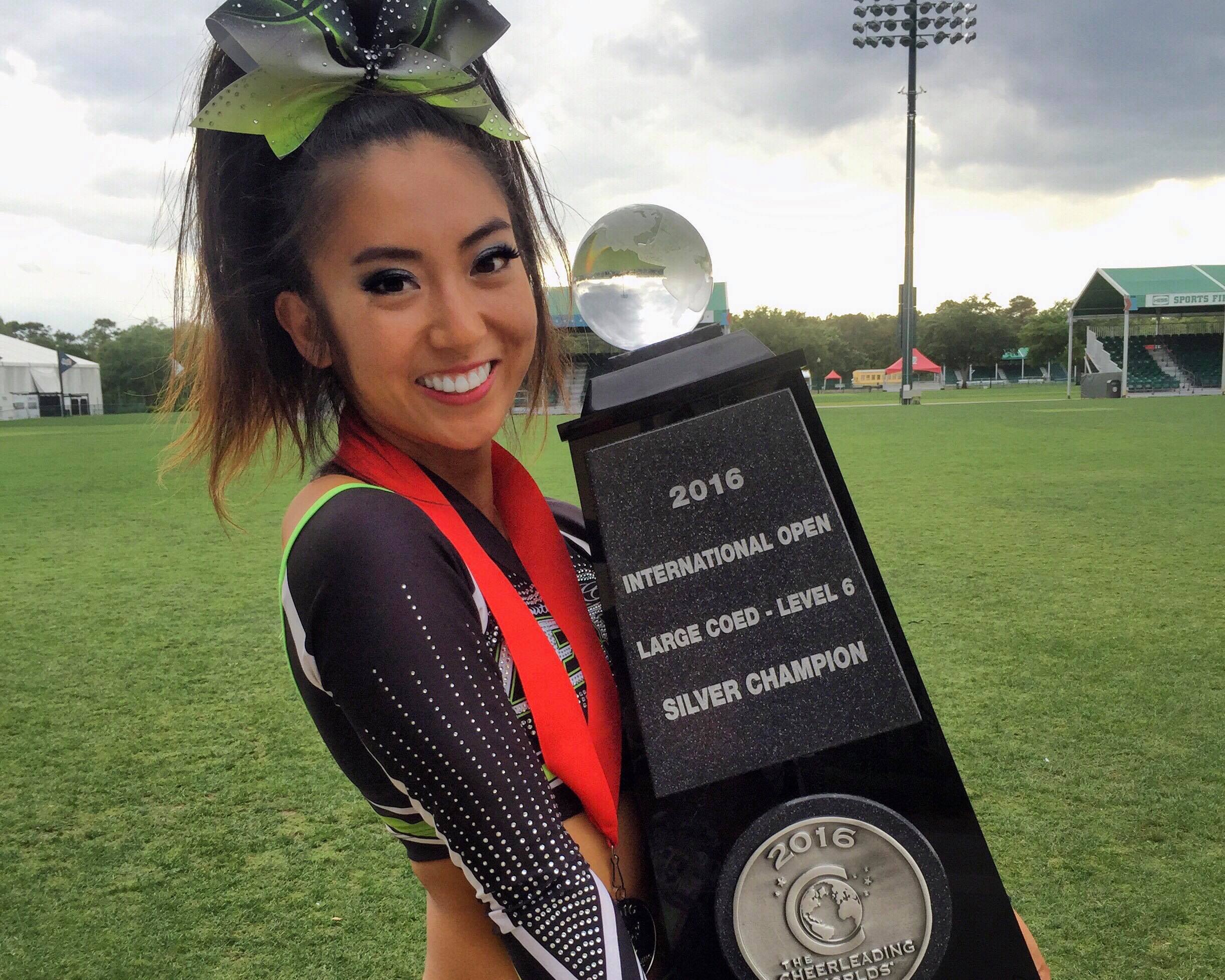



」がサービス提供開始.png)
この記事へのコメントはありません。