
オシム氏の教えが息づく東洋大学サッカー部の育成哲学とは
大学サッカー界で注目を集める東洋大学サッカー部。その強さの秘密は、監督である井上拓也氏が歩んできた独自の指導者人生にあります。ドイツ留学での学び、そして伝説的な指導者イビチャ・オシム氏との出会いが、現在の育成哲学を形作っています。
スポーツコミュニティ株式会社が運営するYouTubeチャンネル「アスキャリ」で公開されているインタビュー動画をもとに、井上監督の指導哲学と東洋大学サッカー部の強さの本質に迫ります。トップレベルの指導者が大切にしている考え方や、選手育成における本質的な視点を知ることができるでしょう。アスリートを目指す方はもちろん、指導者や保護者の方々にとっても、大きな気づきが得られる内容となっています。
ドイツ留学が変えた指導者としての視点
井上監督のキャリアは、体育教員を目指して大阪体育大学に進学したことから始まりました。しかし、その人生を大きく変えたのがドイツのケルン体育大学への留学です。1990年頃のドイツは、サッカー指導において世界最先端の地でした。
ドイツの大学で井上監督が経験したのは、日本とはまったく異なる学びのスタイルでした。日本の大学では教授が前に立ち、学生が受け身で授業を受けるのが一般的です。しかしドイツでは、学期の初日に各学生にテーマが割り振られ、翌週から学生自身が授業の主体となって実践的に運営していきます。授業後にはディスカッションが行われ、最後に教授からフィードバックを受けるという形式でした。
この経験は、井上監督の指導哲学の根幹を形成しています。「自ら考え、実践し、振り返る」というサイクルの重要性を、身をもって学んだのです。帰国後は通訳としてプロチームでキャリアをスタートさせ、その後育成年代の指導者へと転身していきました。
オシム氏から学んだ「考えさせる指導」の真髄
井上監督のキャリアにおいて最も大きな影響を与えたのが、ジェフユナイテッド市原・千葉でコーチを務めた際に出会ったイビチャ・オシム氏です。井上監督は彼を「とんでもなく大きな存在」と表現しています。
オシム氏の指導スタイルで特徴的だったのは、決して安易に答えを与えないことでした。スタッフが選手起用を提案しても、すぐには同意せず、必ず疑問を投げかけてきます。「なぜこの選手を選んだのか」「なぜこの選手を外すのか」と問い続けることで、スタッフ自身に深く考えさせたのです。
印象的なエピソードがあります。コーチ陣が選外とした選手について、オシム氏は「先週、子供が生まれたばかり。ミルクを稼がなきゃいけないだろう」と指摘しました。これは、フィールド上のパフォーマンスだけでなく、選手の人生全体を見る視点の重要性を示しています。

オシム氏の有名な言葉「考えながら走る」には、深い意味が込められています。止まって考えるのは誰にでもできますが、動きながら状況を見て、流れを読んで判断することこそが本当の力だという考え方です。同じミスを繰り返す選手には「走っておいで」と命じました。これは単なる罰ではなく、走りながら自分のミスについて考えろというメッセージだったのです。
また、オシム氏は日本人の特性について鋭い指摘をしていました。「日本人は指導者から提示されたこと以上のものをやらない」という言葉です。与えられた枠組みの中で実行するのは得意でも、新しいものを自ら創造することは苦手だという指摘は、現代の日本のスポーツ界にも通じる課題かもしれません。
東洋大学サッカー部が重視する「熱量」という基準
井上監督が東洋大学の指揮を執るようになったのは、シンガポールや長崎でのアカデミー指導を経た後のことです。東洋大学は10数年前から、Jリーグクラブと提携して大学サッカー部の強化を図るという先進的な取り組みを始めています。
現在、東洋大学サッカー部の部員数は約64名です。学生サッカー界では100名を超える大学も珍しくない中、これは比較的少ない人数といえます。しかし井上監督は、この人数規模にこそメリットがあると考えています。「毎日全員の顔が見えて、言葉を交わせる人数が多い方が良い」という理念のもと、一人ひとりに目が行き届く環境を大切にしているのです。
スカウティングで井上監督が最も重視するのは、技術や実績以上に「東洋大学に来たい、東洋大学でプレイしたい」という熱量です。どれだけ優れた選手であっても、熱意がなければ無理に連れてくることはしません。この姿勢は、チーム全体のモチベーションを高く保つことにつながっています。
「伸び代」を最大化する育成アプローチ
井上監督の指導哲学で特徴的なのは、結果だけでなく「どれだけ伸びたか」を重視する点です。日本一という結果を求めるならベストプレイヤーを選ぶのが近道かもしれません。しかし指導者としてのやりがいは、選手たちのポテンシャルをどれだけ引き出せたかにあると考えています。
東洋大学に入学してくる選手のほとんどは、4年後にプロを目指すという高い目標を持っています。井上監督は学生たちに毎年自分たちで目標を設定させ、それを最後まで自分たちで修正していくことを求めています。この自主性を重んじる姿勢は、オシム氏から学んだ「考えさせる指導」の実践といえるでしょう。
興味深いのは、井上監督の「成功」に対する考え方です。プロになったから成功、一般企業に就職したから失敗という判断は「その瞬間だけ」に過ぎないと語ります。何が成功かは、その後どのように過ごすか、どう自分を成功に導けるかによって決まる、という長期的な視点を持っているのです。

大学サッカーが持つ新たな価値
近年、Jリーグや日本代表において大学卒の選手が増加しています。この背景には、サッカー界を取り巻く環境の変化があります。
Jリーグ発足当初は若手育成のためのサテライトリーグがありましたが、経済的な理由などでクラブが抱える選手数が減少しました。その結果、高校やユースから直接加入した若手選手が公式戦に出場する機会が限られるようになったのです。
一方で大学リーグは高度に組織化されており、明確なカテゴリ分けと毎週の試合が保証されています。4年間でサッカーだけでなく人間的な成長も含めた多様な経験を積んだ22歳の選手は、18歳で入団した選手よりも「即戦力」として評価される傾向が強まっています。
井上監督は選手たちを「導く」というよりも「並走」していきたいと考えています。この姿勢は、選手の自主性を尊重しながら、最大限のサポートを提供するという東洋大学の育成哲学を象徴しています。
YouTubeチャンネル「アスキャリ」では、井上監督の言葉をさらに詳しく聞くことができます。オシム氏とのエピソードや、具体的な指導場面での考え方など、この記事では紹介しきれなかった貴重な内容が満載です。トップレベルの指導者が何を考え、どのように選手と向き合っているのか、その生の声に触れることで、あなた自身のスポーツとの関わり方も変わるかもしれません。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
























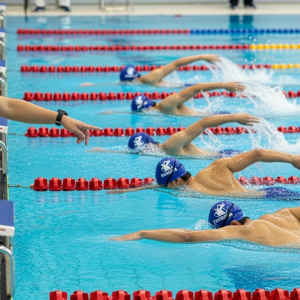
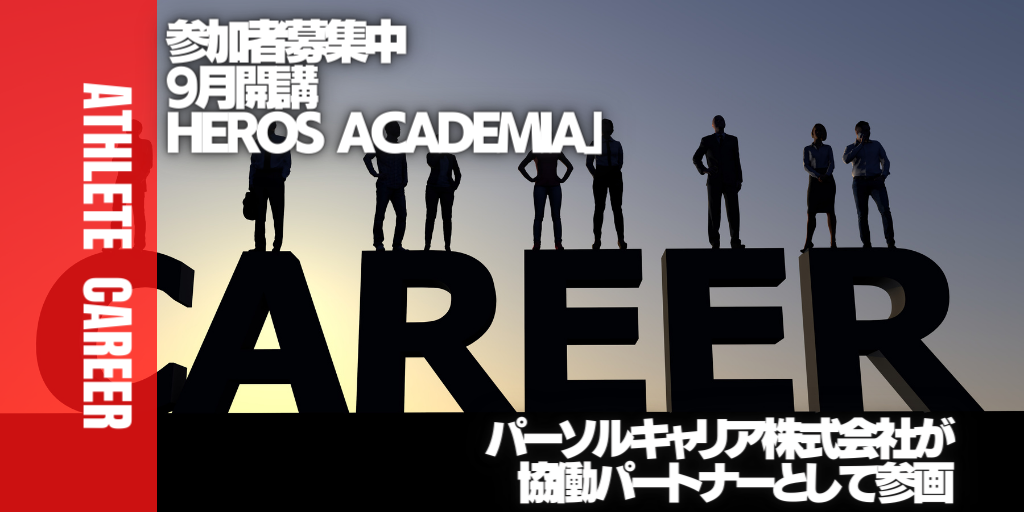


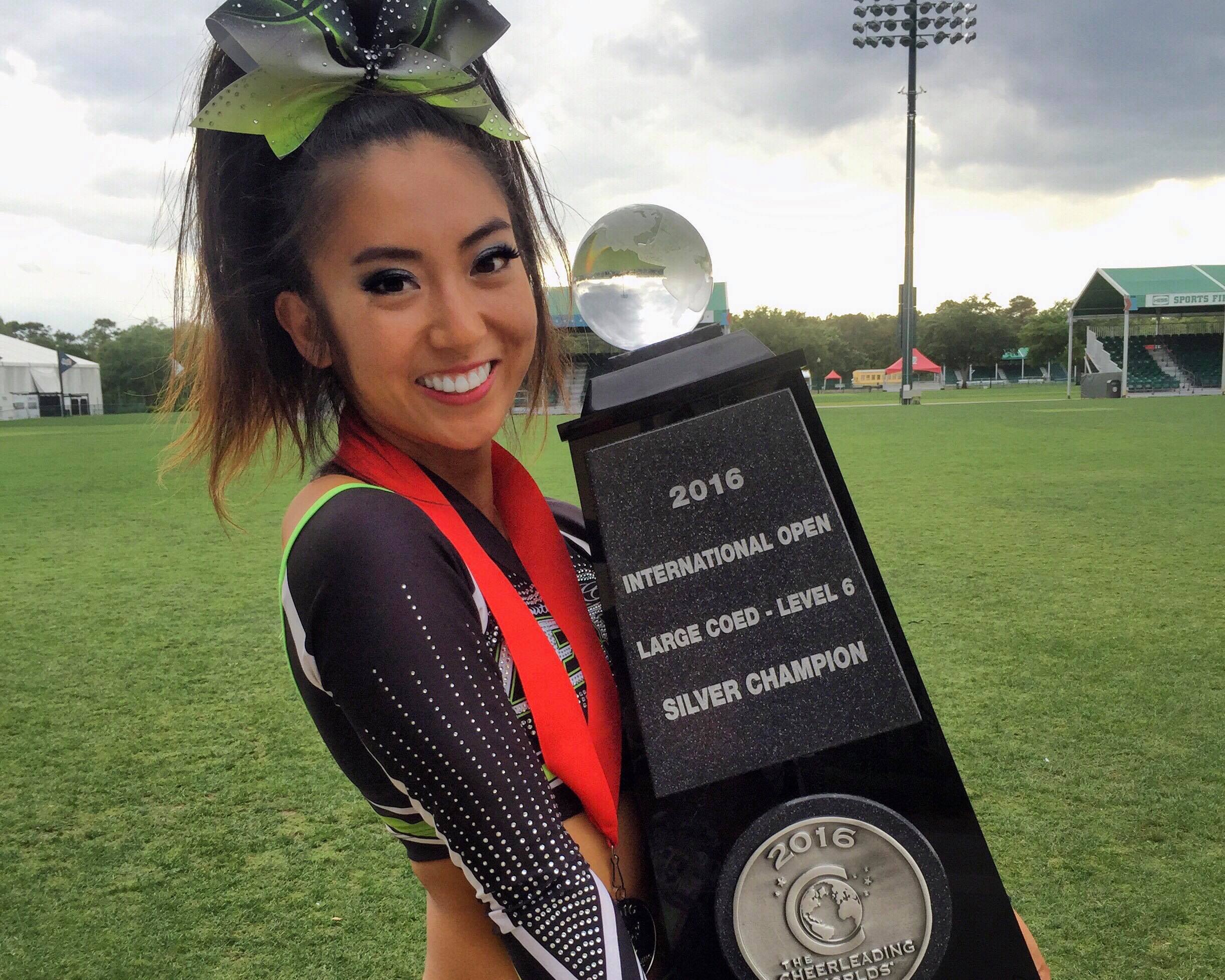

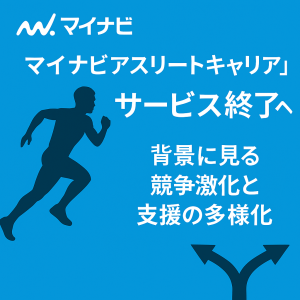
この記事へのコメントはありません。