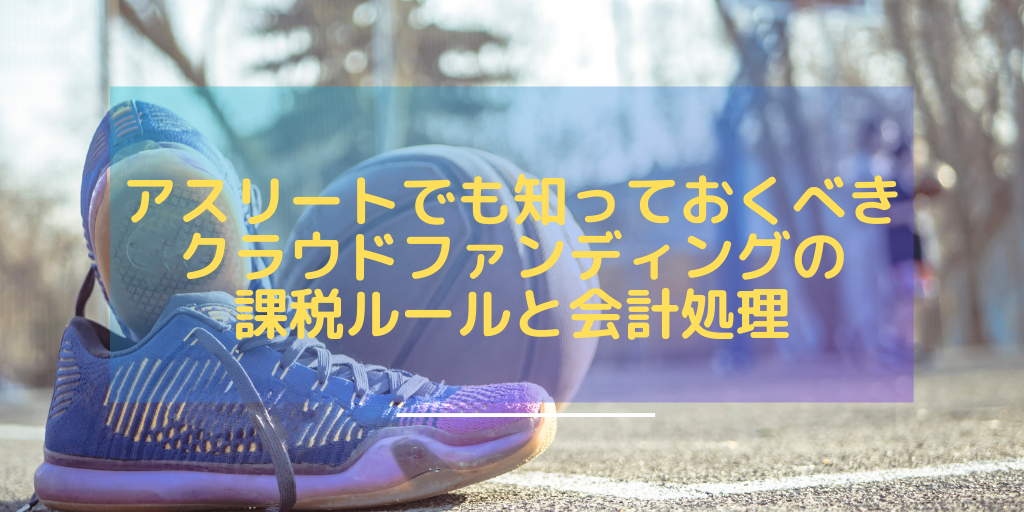
アスリートも知っておくべき…流行りのクラウドファンディングの課税ルールと会計処理
アスリートの資金調達の方法のひとつとしても注目を浴びている「クラウドファンディング(通称:クラファン/CF)」の意外と知られていない課税ルールなどについて解説いたします。
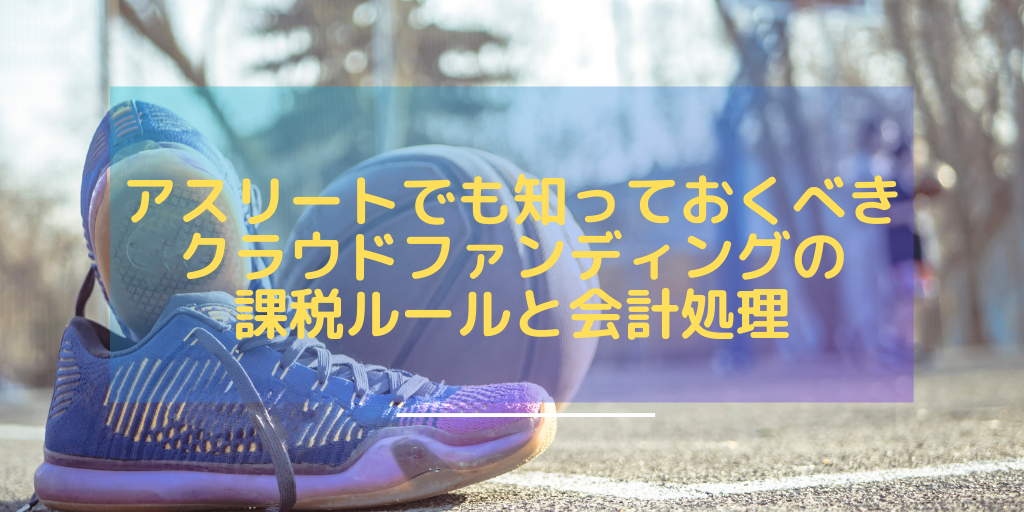
上手くいけば、多くの資金を集めることができますが、クラウドファンディングのように寄付で調達した資金にも税金がかかることがあります。
すべての寄付金に課税されるというわけではありませんが、課税対象になり得る寄付金があった場合、その申告を怠ると「加算税」や「延滞税」など、重いペナルティが課せられることになってしまいます。
クラウドファンディングを利用する前に、どういった場合に税金がかかるのか。またどのように会計処理すればよいか、税務上の扱いについて知っていく必要があります。
クラウドファンディングは資金調達方法のひとつ
クラウドファンディングとは
「Crowd(群衆)」+「Funding(資金調達)」を組み合わせてできた造語で、インターネット上で不特定多数の人から資金を集める行為(資金調達)または、そのサービスのことをいいます。
アスリートは自身の目標や活動を実現するため、ある目的(プロジェクト)を達成するためなど、さまざまな理由で資金が必要な人(プロジェクトオーナー)が、インターネット上で不特定多数の協力者を募り、共感した人が資金を提供するというのはクラウドファンディングです。
クラウドファンディングは、資金提供者や支援者(出資者)への出資のお礼やお返し(リターン)の方法によって、大きく分けて次の「投資型」と「非投資型」に分類されます。
「投資型」は主に3つ
投資型は、「融資型・ファンド型・株式型」の3つに分かれます。
それぞれリターンの方法が異なりますが、金銭的なリターンがあるという点は同じです。
出資者(投資家)がプロジェクトオーナーにお金を貸して、それによって発生した利息や配当金が提供されるという仕組みです。
「非投資型」は主に2つ
非投資型は、「購入型と寄付型」の2つに分かれます。
投資型とは異なり、出資者に対する金銭のリターンは原則ありません。
その代わり、出資のリターンとして、プロジェクトによって完成したモノやサービス、権利などが提供される仕組みになっています。
寄付型は、被災地の支援など社会貢献にまつわるプロジェクトに多く見られます。支援を目的としているため、基本的にリターンはありませんが、お礼の手紙や活動報告が送られてくることもあります。
購入型は、商品やサービスなどを開発するプロジェクトに多く見られます。通常の商品を購入する際と同じ扱いで、予約(受注)販売のようなイメージをすると分かりやすいかもしれません。
出資者はこのうち「寄付型」のみ、出資した金額の一部を「寄付金控除(個人)」または「損金算入(法人)」することが可能です。
ただし、すべてが寄付金控除の対象となるプロジェクトではないため、あらかじめ控除対象かどうかを確認することをおすすめいたします。
多くのアスリートがクラウドファンディングを利用するようになりましたが、この辺りも踏まえた上で実施することをお勧めします。
クラウドファンディングと税金
多くの共感を得ることができれば、何十万万、何百万円というお金が手に入るクラウドファンディングですが、これによって調達した資金は、法人税や所得税の対象となる場合があります。
これは、寄付を受取る側が個人か法人か、また寄付をする側が個人か法人かで、税法上の扱いが異なります。
そこで、クラウドファンディングと税金の関係を、寄付をする側を「スポンサー」、寄付を受け取る側を「アスリート」として解説していきます。
投資型の会計処理
投資型については、金融商品取引法の規制対象となっており、投資型の種類によっても扱いが変わります。
投資型は、「融資型・ファンド型・株式型」の3つからなりますが、「融資型」は、貸付金及び借入金の会計処理と同様になり、「ファンド型・株式型」は、通常の新株発行の会計処理と同様になります。出資者・資金調達者は、資金授受時は税金は発生しませんが、資金運用により得た利益には税金が発生します。
アスリートの場合は、その資金を運用して利益を得るということはまずないと思いますが。
購入型の会計処理
購入型は、ある商品を作るために資金を調達し、出資者はリターンとして完成した商品を受取るという仕組みになっているので、会計上は通常の売買と同じような扱いになります。
これは、出資者・資金調達者が個人・法人のいずれでも同様です。
例えば、調達した金額が100万円で、そこから手数料10%を引かれた額が振り込まれたとします。
この場合は、通常の売買における先払い(手付金)と同様であり、次のように仕訳をします。この時点ではまだ税金が発生しません。
| 日付 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 入金日 | 預金口座 | 900,000円 | 前受金 | 1,000,000円 |
| 手数料 | 100,000円 |
そして、商品が完成し出資者への商品提供が完了したら、前受金を売上に振り替え、次のように仕訳をします。
法人なら益金、個人なら所得が増加するため、この時点で税金が発生します。
| 日付 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 商品提供日 | 前受金 | 1,000,000円 | 売上高 | 925,926円 |
| 消費税 | 74,074円 |
通常の売買と同様の扱いのため、課税事業者であれば購入型で調達した資金(売上)は、課税売上となります。また、個人の場合このときの所得区分は、事業から生ずる所得であれば「事業所得」、当てはまらない場合は「雑所得」になります。
資金調達者がサラリーマンだったとき
あまりないケースかもしれませんが、資金調達者がサラリーマンなどの給与所得者だった場合で、次に当てはまる場合は確定申告をする必要があります。
- クラウドファンディングで生じた所得(売上 – 経費)が、年間20万円を超えた場合
- 給与年収が2,000万円を超えた場合
- 還付申告をしたい場合
ただしこれらに当てはまらず、確定申告をしない場合でも、住民税申告は必要になりますので注意してください。
寄付型とみなされることもある
調達した金額より、リターンの価値が極端に低い場合は、寄付型とみなされる場合がありますので注意が必要です。アスリートによるクラウドファンディングで高額なものはこちらに該当することがありますの注意が必要です。
例えば、出資者が100万円提供した場合のリターンが、価値が10,000円相当の物品提供のみ、という場合は、寄付型と判断されてしまう可能性があるということです。
寄付型の会計処理
寄付型は、リターンなしで資金を調達するので、贈与を受けたと同じ扱いをします。アスリートによるクラウドファンディングではこのケースが一番多いと思います。
会計処理のケースは次の4つに分かれます。
1.「個人」→「個人」
個人から個人の場合、寄付は贈与とみなされるため、贈与税が発生します。贈与税は、基礎控除の110万円を超えて寄付を受けたときに発生します。
2.「法人」→「個人」
法人から個人の場合、一時所得扱いとなります。一時所得の金額は、「総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) 」で算出します。
3.「個人」→「法人」
個人から法人の場合、寄付は贈与とみなされ受贈益が増えるため、法人税が発生します。また、プロジェクトに必要な費用と手数料は、必要経費として損金算入することが認められています。
4.「法人」→「法人」
法人から法人の場合も、(3)のケースと同様です。(3)(4)ともに次のような仕訳をします。
| 日付 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 入金日 | 預金口座 | 〇〇円 | 受贈益 | 〇〇円 |
おわりに
今回は、資金を受け取った側のアスリートの税務上の扱いについて解説しました。
受け取った資金について、計上が漏れていたり、申告を忘れていると重たいペナルティ(加算税・延滞税等)が課せられてしまいます。クラウドファンディングを利用する際は、このような税金が関わっているということも念頭においておくと良いでしょう。
併せてこちらの記事もご覧ください。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



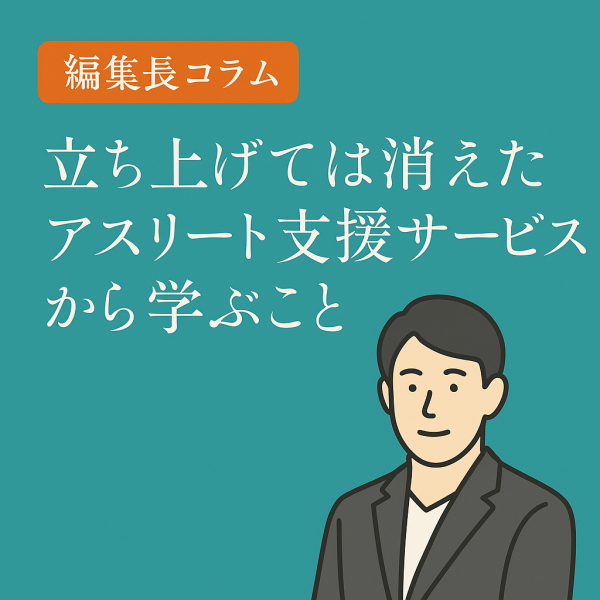
の勘定科目-600x450.png)











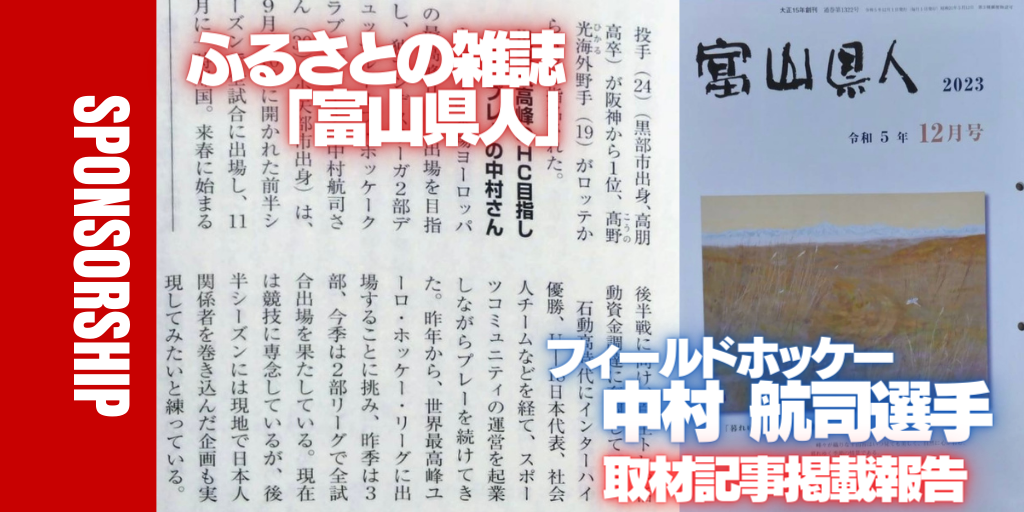



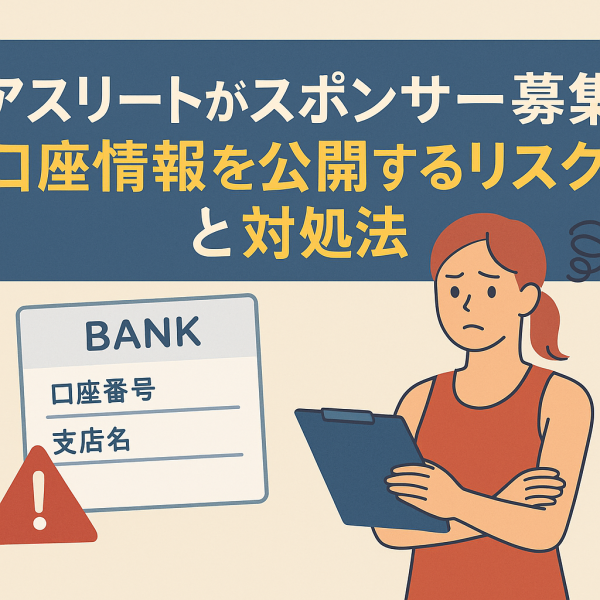




















この記事へのコメントはありません。