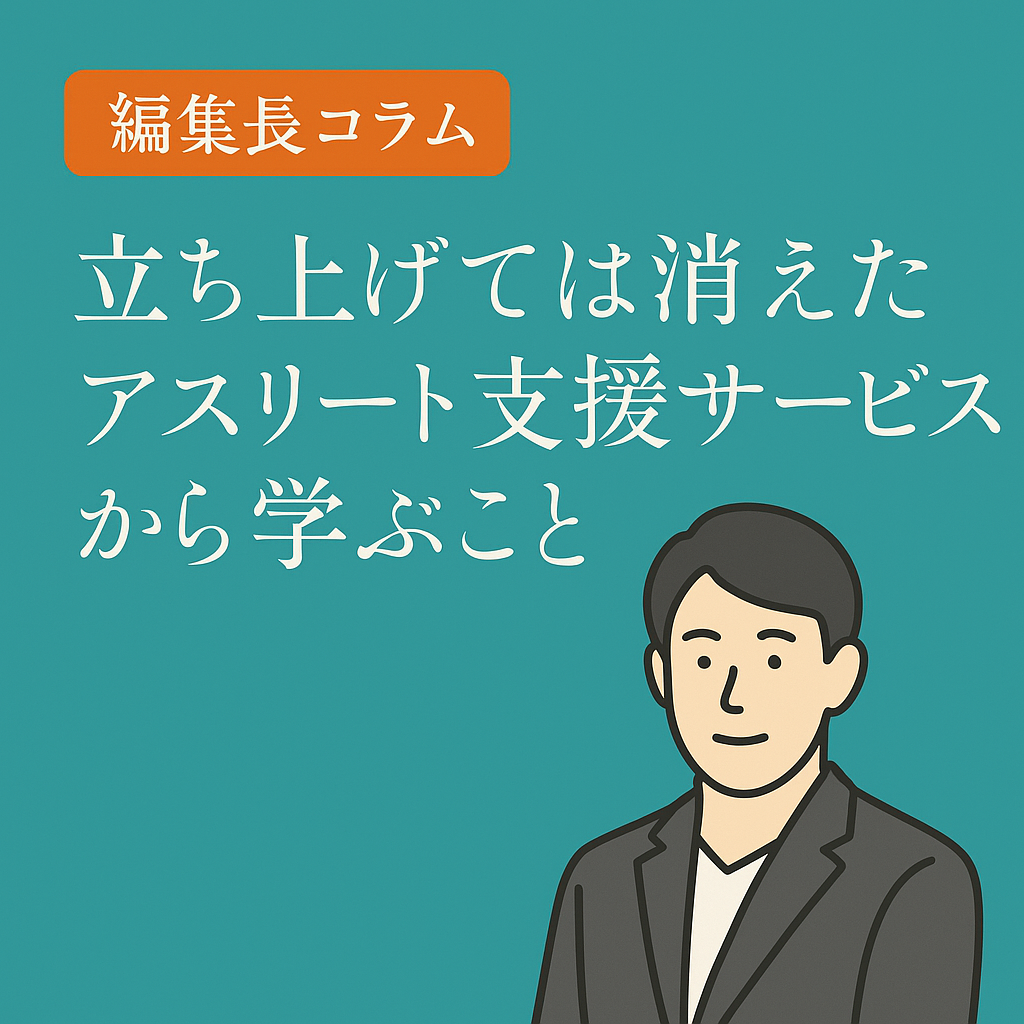
【編集長コラム】立ち上げては消えた「アスリート支援サービス」から学んだことと、Find-FCが目指すもの
アスカツ編集長の吉沢です。いつもアスカツをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。久しぶりの編集長コラムになります。
この10年ほどの間に、日本では「アスリート支援サービス」が数多く誕生してきました。クラウドファンディングに特化したもの、スポンサーと選手をつなぐマッチング型、ファンクラブやサブスク形式、さらにはNFTやトークンを活用した最新型まで…。その時々で注目を集め、大きな期待を背負って立ち上がったサービスは少なくありません。
しかし、話題になったはずのサービスが気が付くと更新を止め、ひっそりと姿を消してしまう例を私は何度も目の当たりにしてきました。立ち上げに関わった方々は皆、「選手を支えたい」という真摯な思いを持っていたにもかかわらず、続けることの難しさに直面していたのです。
では、なぜ多くのサービスは定着できなかったのか。そしてアスカツの姉妹サービスであるアスリート支援のプラットフォーム「Find-FC」は、どうすれば同じ轍を踏まずに持続可能な仕組みを築けるのか。本コラムでは、その答えのヒントを共有したいと思います。
日本で過去に存在したアスリート支援サービス(縮小・消滅含む)
1. マッチング系
-
SpoPla(スポプラ)
アスリートとスポンサーをつなぐ国内プラットフォーム。初期は注目されたがスポンサー登録が伸びず休止。 -
SPIN(スピン)
競技・大会ごとにスポンサーを募集する試み。大手スポンサー契約が生まれず消滅。 -
アスリートオーナー
スポーツ選手の“オーナー”になれる仕組みとして話題に。投資的な要素を含んだが、法的整理や収益モデルが難しく広がらず。
2. ファンクラブ/サブスク系
-
FAVs(ファブズ)
アスリートやクリエイターのファンクラブを月額制で運営できる仕組み。利用者が伸びず撤退。 -
MOTTAINAIスポーツ
個人競技選手の「応援サロン」型サービス。短命で終了。 -
athlete yell(アスリートエール)
「月額応援」形式でアスリートに継続支援できる仕組みを展開。SNS発信やグッズ連動を模索したが、大規模化には至らず活動縮小。
3. クラファン特化型
-
JustGiving Japan(2010〜2019)
世界的には有名だったが、日本での寄付文化の未成熟により撤退。アスリート支援にも多く使われた。 -
アスリート専用クラファン系スタートアップ(複数)
READYFORやCAMPFIREに吸収、またはサービス終了。
4. Web3/トークン系
-
FiNANCiE(フィナンシェ)スポーツ部門
NFTトークンを通じた応援・資金調達モデル。初期は盛り上がったがWeb3市況悪化で縮小。
5. その他
-
アレJAPAN
「日本代表を応援する」コンセプトで立ち上がった仕組み。特定スポーツやナショナルチーム応援企画として注目されたが、長期的には広がらず停滞。
まとめ
こうして見ると、形は違えど「寄付型」「サブスク型」「投資型」「Web3型」など多様なモデルが試されてきました。
しかしどれも 「持続性の欠如」「スポンサー実利の不明確さ」「アスリート側の発信負担」 という壁にぶつかり、規模拡大や定着には至らなかったのが共通点です。
-1024x596.png)
なぜ続かなかったのか
スポンサーから見ると“寄付”で終わってしまう
たとえばクラファン型は大会遠征前に一時的な盛り上がりを見せても、スポンサーにとっては「寄付」で終わってしまい、PR効果や顧客接点が不十分でした。
例:athlete yell は「月額応援」という画期的な仕組みでしたが、スポンサーにとってのリターンが弱く、長期継続につながりませんでした。
発信力のある一部の選手しか恩恵を受けられない
SNSフォロワーが多い選手は注目を集められる一方で、競技に専念して発信が少ない選手は支援が得にくい構造がありました。
例:アスリートオーナー は「選手のオーナーになれる」というユニークな仕組みでしたが、投資が発信力の強い選手に集中し、広がりを欠いたまま停滞しました。
平時の支援が仕組み化されていない
大会直前は「応援しよう!」という機運で支援が集まっても、普段の練習費・用具費・生活費を支える仕組みは十分ではありませんでした。
結果として、支援は“点”で終わり、アスリートの「日常」を下支えできなかったのです。
失敗から見える教訓
こうした事例から私が学んだのは、「善意だけでは続かない」という現実です。
アスリートもスポンサーも、そしてサービスを運営する側も、それぞれが“持続できる理由”を見つけられなければ、どれほど熱意を持って始めても長続きしません。
だからこそ、次に求められるのは「選手・スポンサー・ファンの三者が、それぞれ価値を感じられる仕組みづくり」です。
Find-FCが大切にしていること
私はFind-FCを運営するうえで、アスリートと日々向き合うことを一番大事にしています。
オンラインの仕組みだけでは見えないことが、リアルの会話にはたくさんあります。
「仕事が忙しくトレーニングの時間がなかなかとれない…」仕事と競技との両立の悩み、練習の合間に聞く「今日は調子悪くて…」という声、スポンサーにどう感謝を伝えたいかという悩み、競技のことだけじゃなく「地元で子どもたちに教えるのが楽しい」という笑顔。
こういう人間味のある一面を知ると、応援する側の気持ちはもっと強くなる。だからこそ、私は編集長として記事やインタビュー、そして、昨今ではPODCAST チャンネルなどを通じて、その人間性を引き出して伝える努力をしています。
Find-FCの挑戦
1. スポンサーの実利を明確化
寄付ではなく「広報」「ブランド価値」「顧客接点」といったマーケティング投資としてスポンサーに還元する。
→ 実際にスポーツクリニックやジュエリーブランドがFind-FC経由でアスリートを支援し、自社PRに活用する事例が生まれています。
2. 選手の発信力に依存しない仕組み
発信が苦手な選手でも、アスカツ編集部が記事を作成し、Find-FCチャンネルで動画を発信。選手は競技に集中しながら、自然に露出が増えるよう設計しています。
3. マイナースポーツ横断のコミュニティ化
パデル、ジャンプロープ、ステアクライミング、フレスコボール、ビーチハンドボールなど、単独競技では小さな波でも、複数競技がつながれば大きな“面”となり、スポンサーも支援しやすい。Find-FCはこの「横のつながり」を強みにしています。
4. リアルコミュニケーションで人間性を伝える
そして何より私自身が日々アスリートと直接対話し、彼らの悩みや夢を聞き、人としての魅力を引き出すことにこだわっています。
「競技の成績」だけでなく、「人としての物語」をスポンサーやファンに届ける。これこそがFind-FCの最大の価値だと考えています。
5. アスリートを“運営側”に巻き込む仕組み
Find-FCでは、単に「支援される側」として選手を位置づけるのではなく、運営にも携わってもらうことを大切にしています。
登録アスリートが広報や企画業務をサポートし、自らの経験を活かしてサービス運営に参加することで、「共に作り上げるプラットフォーム」としての一体感が生まれています。
6. Kプロデュース株式会社との事業連携
Find-FCを運営する Kプロデュース株式会社 は、主幹事業としてウェブマーケティングを手がけています。
このノウハウを活かし、スポンサー企業には最適化されたプロモーション提案を、選手には露出機会の最大化を提供。さらに、業務委託の形でアスリート自身にマーケティングの一部を任せるなど、実務を通じたキャリア形成の場もつくっています。
7. アスリートのキャリア支援
競技生活だけでなく、その後の人生設計も視野に入れたキャリア支援を推進。
マーケティング業務の実務経験や、スポンサーとのネットワーク構築を通じて、アスリートが「引退後も社会で輝ける力」を培うことをサポートしています。
終わりに
これまで立ち上がっては消えていったサービスを振り返ると、「どうして続かなかったのか」という答えが浮かび上がってきます。
しかし同時に、それは私たちにとって大きな学びであり、次の挑戦に活かせる教訓でもあります。
Find-FCは仕組みだけでなく、アスリート一人ひとりと向き合い、人間性を伝えることを通じて、支援を“点”で終わらせず、“線”や“面”に広げていくことを目指しています。
その一方で、Find-FCの運営者として、現在では150名を超えるアスリートに登録いただけるまでになりました。これは本当にありがたいことですが、一方で、すべての選手に十分かつ満遍なくサポートが行き届いているわけではありません。その実態に対しては、私自身強い責任を感じ、申し訳なく思っています。限られたリソースの中で、どうすれば一人ひとりの選手によりよい支援を届けられるのか、日々模索を続けています。
私たちは、競技生活を支えるだけではなく、運営参画やマーケティング業務の経験提供を通じて、アスリートのキャリア支援にも取り組んでいます。スポーツをしている「今」だけでなく、競技人生を終えた「その先」も輝けるように、選手たちの未来まで見据えて伴走していきます。
アスリート、スポンサー、そしてファンの三者がそれぞれ価値を感じ、共に歩めるプラットフォームであること。
それがFind-FCの使命であり、日本のスポーツをもっと強く、もっと面白くしていく道だと信じています。
文:吉沢協平(Find-FC代表/アスカツ編集長)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



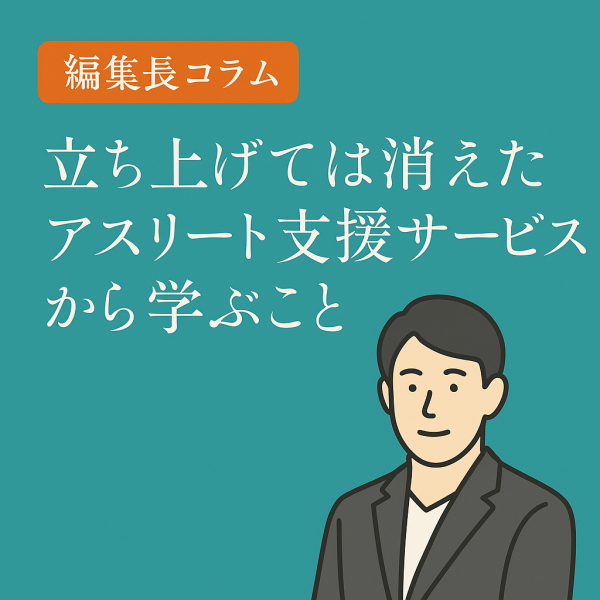
の勘定科目-600x450.png)











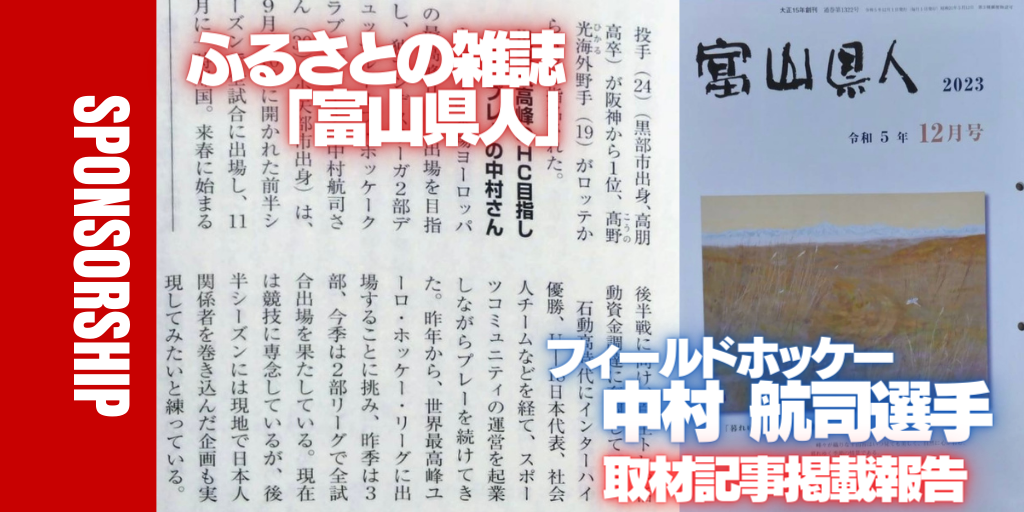


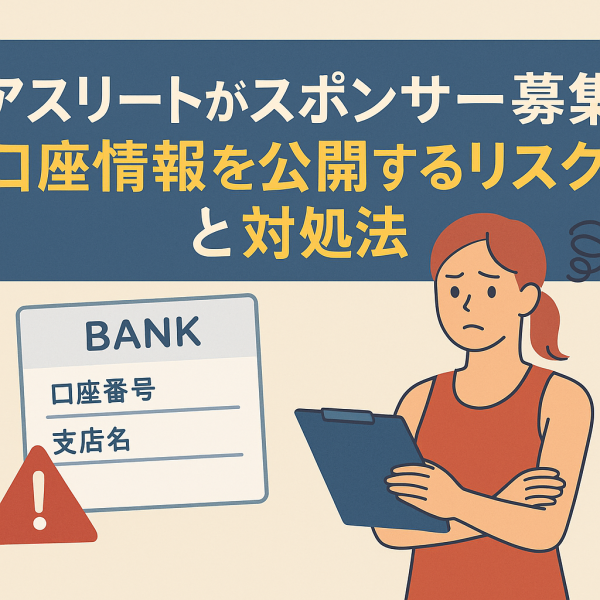














に入団!その真価が問われる挑戦!.png)


の勘定科目-300x300.png)
この記事へのコメントはありません。