
インフルエンサーアスリートの“賞味期限”とは?終わる前に必ずやっておきたいビジネス戦略
SNSで大きなフォロワー数を持ち、スポンサーや企業からの注目を集める「インフルエンサーアスリート」。しかし、その人気や影響力には必ず“賞味期限”が存在します。アルゴリズムの変化やフォロワーの興味の移り変わり、競技成績の浮き沈みによって、注目度は常に変動するからです。では、その賞味期限を迎える前に、アスリートは何をしておくべきなのでしょうか。
収益モデルを多角化する
単発の案件やSNSでの広告収入に依存するのは危険です。講演活動、イベント主催、オリジナルグッズ販売、オンラインサロンといった複数の収益源を持つことで、安定的なキャッシュフローを確保できます。これは企業でいう「事業ポートフォリオ戦略」と同じ考え方であり、アスリート自身が経営者の視点を持つことが重要です。
ブランドを「企業価値」として育てる
インフルエンサーアスリートにとって、自身は“ブランド”そのものです。ロゴやスローガン、活動ビジョンを明確にし、スポンサーと「共創」できる形に育てることで、単なる広告塔ではなく、企業にとって長期的に価値あるパートナーとなります。
事例:石川祐希選手
日本バレーボール界のエース、石川祐希選手は「デサント」「SKINS」「ポーラ」など複数のブランドとアンバサダー契約を結んでいます。単発の広告案件ではなく、ブランドと共に価値を高め合う長期的な関係を築くことで、現役中はもちろん引退後にもつながる“資産化されたブランド価値”を生み出しています。
データとファンを自分の資産にする
SNSは強力なツールですが、プラットフォームのルールひとつでリーチが激減することもあります。だからこそ、メールリストや会員サイト、LINE公式アカウントといった“直接つながれるチャネル”を育てることが不可欠です。ファンとの関係を「フォロワー数」から「顧客データベース」へ移行させることは、企業のCRM戦略そのものです。
法務・契約・税務の基盤を整える
影響力が大きくなるほど、案件契約や税務処理のリスクも増大します。一定の収入が見込める段階で、法人化を検討するのも有効です。法人化によって節税効果が得られるだけでなく、スポンサー契約において「信用度」が増すというメリットもあります。
事例:法人化・起業するアスリートの増加
近年は現役アスリートが自ら会社を設立し、スポンサーとの交渉やキャリア事業を進めるケースも増えています。税務面の安定、顧問士業との連携、経営基盤づくりは「アスリート兼経営者」としての必須スキルとなりつつあります。
引退後を見据えたキャリアデザイン
賞味期限を迎える前に、次のキャリアを描き始めることが大切です。競技指導、講演、企業アドバイザー、スクール運営など、自身の専門性を別の軸に展開する準備を早めに進めるべきです。
事例:スポーツ系YouTuberのスポンサー戦略
プロゴルフコーチが運営する「DaichiゴルフTV」は、企業とコラボしてカード会社のキャンペーンや視聴者参加型企画を実施。これによりYouTubeという発信の場が、単なる動画投稿から「スポンサー企業の広報活動の一部」へと昇華しました。こうした取り組みは、引退後や競技外の活動でも持続的に価値を生み出す好例です。
まとめ
インフルエンサーアスリートにとって、今の人気や影響力は永遠に続くものではありません。だからこそ、注目度が高いうちに「収益の多角化」「ブランド価値の構築」「ファンの資産化」「法人化と経営基盤整備」「次のキャリア準備」を進めることが重要です。石川祐希選手のようにブランドと共に成長し、法人化によって安定性を高め、YouTuberのようにスポンサーを巻き込んだ発信を行うことで、賞味期限を超えても輝き続ける道が開けるのです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



























-300x300.png)
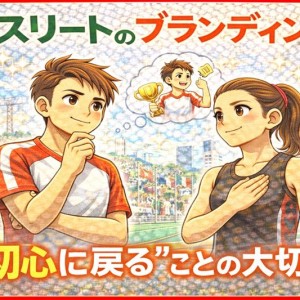


この記事へのコメントはありません。