
ビーチハンドボール日本一チームが示す、アスリートの新しいキャリアの形
インドアハンドボールを引退した後も、競技を続けたい。世界で戦いたい。そんな思いを実現させたのが、ビーチハンドボール女子チーム「SWAG(スワッグ)」です。全日本2連覇を達成したこのチームは、選手自らがチーム運営を行い、クラウドファンディングで資金を集め、海外挑戦を続けています。
アスリートのセカンドキャリアというと、引退後の就職支援をイメージする方が多いでしょう。しかし、競技を変えることで現役生活を延ばし、新たな目標に挑戦するという選択肢もあります。YouTube「アスキャリ」で紹介されたSWAGの取り組みは、アスリートが主体的にキャリアを切り開く姿を鮮明に映し出しています。本記事では、チームのキャプテン、ゴールキーパー、ポストプレーヤーへの密着取材をもとに、マイナースポーツでも世界を目指せる環境づくりと、アスリートが持つべき視点について詳しく解説していきます。
インドアから転向して見えた、ビーチハンドボールの新たな可能性
ビーチハンドボールは、インドアハンドボールとは全く違うスポーツです。最大の特徴は、1回転(スピン)しながらシュートを打つなど、アクロバティックなプレーが得点につながる点にあります。音楽が流れる中でダイナミックなプレーが繰り広げられる光景は、観客を魅了する要素に満ちています。
インドアハンドボールとの大きな違いは、オフェンスとディフェンスの人数が異なることです。これにより戦術や戦略が大きく変わり、競技としての面白さが生まれています。さらに注目すべきは、ゴールキーパーでも得点が取れるという点。守りだけでなく攻めのゴールキーパーができることは、ポジションの価値を大きく広げています。
以下の表は、インドアハンドボールとビーチハンドボールの主な違いをまとめたものです。
| 項目 | インドアハンドボール | ビーチハンドボール |
|---|---|---|
| プレースタイル | 組織的な攻防 | アクロバティックなプレー |
| 人数バランス | オフェンス=ディフェンス | オフェンス≠ディフェンス |
| ゴールキーパー | 守備専門 | 得点も狙える |
| 競技環境 | 室内コート | 砂浜(怪我しにくい) |
| 雰囲気 | 静粛な観戦 | 音楽が流れる楽しい空間 |

SWAGのメンバーは、元々インドアハンドボールの選手でした。転向当初は、1回転してシュートを撃ってくるためタイミングが掴みにくく、ディフェンスがシュートの際に間にブロックに入ってくるなど、インドアにはない戸惑いもあったといいます。しかし、砂浜という環境は怪我をしにくく、インドアハンドボールを引退した後でも始めやすいという大きなメリットがあります。
水泳や野球など他のスポーツ経験者でも楽しめる点も魅力です。ディフェンス、キーパー、オフェンスのどのポジションでも得点が取れて輝けるため、様々なバックグラウンドを持つアスリートにとって、新たなキャリアの選択肢となっています。
「世界で勝つ」ために自分たちで作り上げたチーム運営
SWAGは2019年、日本代表の一部メンバーが中心となって結成されました。当時のアジア選手権で戦った経験から、「もっとアジアに勝っていきたい」「世界に羽ばたきたい」という強い思いが芽生え、世界で勝てるチームを作ろうという決意のもとスタートしたのです。
チームの最大の特徴は、マネージャーや監督が全て運営を行うのではなく、選手自らがチーム運営を担っている点にあります。練習場所の確保から費用の捻出まで、全てを自分たちで行わなければなりません。メンバーは遠方から集まっているため、費用面での課題は常につきまといます。
この課題に対し、SWAGは独自の工夫を凝らしています。練習場所を東海と関東で交互に設定し、試合の場所や時期も考慮しながらバランス良く組むことで、メンバーの負担を軽減しています。さらに、練習後はホテルを取らず、毎回メンバーの家に宿泊することでコストを抑えているのです。
オフの過ごし方も特徴的です。食べ放題に行くのが恒例となっており、毎回満腹になるまで食べるそうです。メンバーの家ではゲームをしたり、焼きそばを作ったりして過ごすなど、チームの絆を深める時間を大切にしています。

チームの強みは、年齢に関係なく誰とでもコミュニケーションが取れる点にあります。年上の頼りになるメンバーが多く、わからないことを聞くと「1聞けたら10返ってくる」くらい丁寧に教えてくれる関係性が築かれています。一人ひとりが自分のポジションの能力を最大限に発揮するために日々努力し、「他のポジションもやってみよう」という好奇心を持ってお互いを高め合っているのです。
以下は、SWAGのチーム運営の実態をまとめた表です。
| 運営項目 | 一般的なチーム | SWAG |
|---|---|---|
| 練習場所の確保 | マネージャーが担当 | 選手自身で確保 |
| 費用の捻出 | スポンサー中心 | 自己負担+クラウドファンディング |
| 宿泊 | ホテル手配 | メンバーの家に宿泊 |
| 練習場所 | 固定 | 東海と関東で交互 |
| チームの雰囲気 | 階層的 | 年齢関係なくフラット |
クラウドファンディングで実現した海外挑戦と見えてきた課題
コロナ以降、日本代表の活動がなくなり、チームコンセプトである「世界に通用するチーム」を達成できずにいました。この状況を打破するため、SWAGは今年、チームとして海外挑戦への参加を決意します。
資金面での課題を解決するため、チームはクラウドファンディングを実施しました。以前、2人のメンバーが個人で海外挑戦した際にクラウドファンディングを行った経験があり、その知見を活かしたのです。目標は300万円でしたが、150万円でも大きな支えになったといいます。資金面で困っているチームメイトの助けになることが、実施の大きな動機でした。
海外での経験は、チームに明確な課題を突きつけました。海外の選手は、スピン(1回転シュート)だけでなくスカイシュートを多く使い、それによって得点を多く取っていることが分かったのです。オフェンス面での課題が明確になったことで、今後の強化ポイントが見えてきました。
体格差については物理的に勝てないため、スピードで高さを突破していくことを意識しています。いかにディフェンスが来ない間にシュートを打ちに行くか。この戦略的な視点が、世界で戦うための鍵となっています。
マイナースポーツだからこそ生まれる、アスリートと観客の距離感
ビーチハンドボールは、現在無料で観戦できる試合がほとんどです。全日本大会などでは、うちわを作って応援してくれるサポーターもおり、選手たちは日々パワーをもらっているといいます。マイナースポーツならではの、アスリートと観客の近い距離感が、競技の魅力を高めているのです。
SWAGのメンバーは、応援してくれる方々への感謝を忘れず、「プレーや結果で返したい」と考えています。今後も海外挑戦などを通じて、「やっぱり面白いスポーツだ、応援したくなるスポーツだ」と思ってもらえるように頑張りたいと意気込みを語っています。
動画では、メンバーの生の声や練習風景、チームの雰囲気がより詳しく紹介されています。自分たちでチームを運営し、世界を目指すアスリートたちの姿は、きっとあなたのキャリア形成のヒントになるはずです。YouTube「アスキャリ」で、SWAGの挑戦の全貌と、ビーチハンドボールという競技の奥深さを体感してください。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
























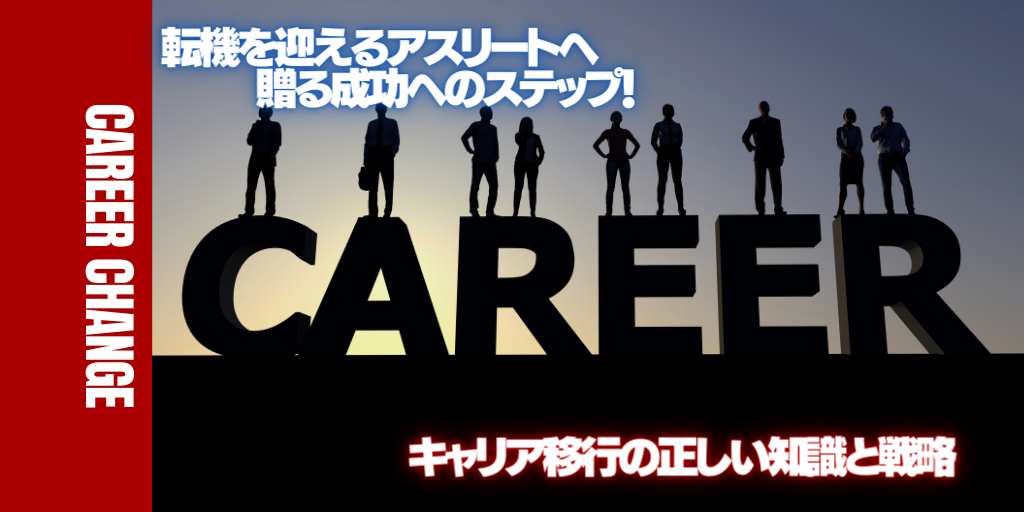




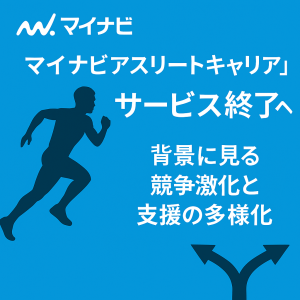

この記事へのコメントはありません。