
日本一の監督が語るサッカー指導の真髄
「考えながら走る」――この言葉には、サッカーというスポーツの本質が凝縮されています。スポーツコミュニティ株式会社が運営するYouTubeチャンネル「アスキャリ」では、東洋大学サッカー部を全国大会優勝に導いた監督が、日本代表監督も務めた名将イビチャ・オシム氏から学んだ指導哲学について赤裸々に語っています。
この記事では、その対談動画の内容を詳しく紹介しながら、世界レベルの指導者が持つ視点、ドイツでの学びが日本の指導にどう活かされているのか、そして現代の大学サッカーが果たす役割について深く掘り下げていきます。サッカー指導者はもちろん、教育に携わる方々、さらにはビジネスの現場でチームを率いる立場にある方々にとっても、多くの気づきが得られる内容となっています。この記事を読むことで、一流の指導者が大切にしている思考法と、それを実践に移すための具体的なアプローチが見えてくるはずです。
大学とJリーグクラブの先進的な提携モデル
東洋大学サッカー部の監督は、大宮アルディージャから大学へ業務提携という形で派遣されています。各国の代表監督と仕事を経験してきた経歴を持つ人物が大学生を指導するのは、大学サッカー界では珍しいケースです。
しかし、近年ではJリーグのクラブと大学が提携する形が増えてきています。東洋大学のこの取り組みは先進的であり、このシステムは10数年前から行われており、現在の監督は4代目にあたります。
このモデルの最大の利点は、プロの現場で培われた知見と経験を、次世代を担う大学生に直接伝えられることにあります。近年、高校のトッププレイヤーが直接Jリーグへ行くのではなく、大学卒が代表チームのメンバーに増えているというトレンドの変化も、こうした取り組みの成果と言えるでしょう。

ドイツ留学で学んだ主体的な学びのスタイル
東洋大学の監督は、大阪体育大学を卒業した後、ドイツのケルン体育大学へ留学しました。1990年、イタリアワールドカップでドイツが優勝した年のことです。当時のドイツはサッカー指導においてトップクラスであり、日本の指導者ライセンス制度もドイツから導入された経緯がありました。
ドイツの教育現場で最も驚いたのは、その授業形態でした。日本の体育大学の授業が、先生が前に立って学生が受け身で聞く対面形式が多いのに対し、ドイツの授業は実践的だったのです。
ドイツと日本の教育スタイルの違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 日本の体育大学 | ドイツの体育大学 |
|---|---|---|
| 授業形式 | 教員が前に立ち学生が聞く受動的スタイル | 学生が主体的に授業を行う能動的スタイル |
| 学びの進め方 | 教員からの一方的な知識伝達 | 学生同士のディスカッションと教授のフィードバック |
学期の初日に学生それぞれに授業のテーマが割り振られ、次週からは学生が主体的に授業を行い、他の学生とのディスカッションを経て、最後に教授からフィードバックを受けるという形式でした。この画期的な授業形態を30年前に経験したことが、今の指導のベースになっていると監督は語っています。
ドイツでの留学期間は3年間でしたが、当時SNSやインターネットがない時代で、ドイツ語の習得は簡単ではありませんでした。午前中に語学学校に通い、午後に授業を受けていましたが、100%理解できないため、同じ授業を2学期にわたって継続して受けることもあったといいます。
オシム氏から学んだ「決めつけるな」の哲学
帰国後、当初は指導者としての契約が得られず、通訳としてスタートし、数年後に育成の指導者になりました。その後、ジェフユナイテッド市原(当時)に入り、日本代表監督も務めたイビチャ・オシム氏と出会います。オシム氏は監督にとって「とんでもなく大きな存在の人」であり、非常に大きな影響を受けました。
オシム氏は愛情がある人で、スタッフや選手から嫌われることはありませんでした。彼はメディアが捉える「いい選手」(ゲームメーカーなど)だけではなく、チームが成り立つバランスを常に考慮していました。
特に印象的だったのは、オシム氏の「決めつけるな」という姿勢です。コーチ陣が選出メンバーを提案する際、その理由付けを厳しく問いただしました。例えば、ある選手を外す提案をした際、オシム氏は「この選手は先週子供が生まれたばかりだ。ミルクを稼がなければいけないだろ」といった、コーチ陣とは異なる目線や視点で指摘をすることがありました。
しかし、コーチ陣がその指摘を参考にして次週同様の視点で提案すると、今度は「どこを見ているんだ」と激しく批判されることもあったといいます。これは単なる気まぐれではなく、スタッフに対して「無理」や「難しい」と簡単に言わせない姿勢を、日々の小さな要求の積み重ねを通じて鍛え上げていたのです。
「考えながら走る」サッカーの本質
オシム氏の指導哲学の核心にあったのが「考えながら走る」という概念です。彼の前提は「歩きながらサッカーできないでしょ」というものでした。
止まって考えるのは誰でもできますが、動きながら状況を見て、流れを見て考えることが重要でした。選手がチャレンジによるミスは許容しつつも、同じミスを繰り返すのは、「ミスをミスではないと勘違いしているか、何も考えなかったから」だとし、その際は「走っておいで」と命じました。
もし指導や持っていき方が悪かった場合、スタッフも「考える時間を与える」として一緒に走らされることがありました。この厳しさの背景には、選手に対して「自分で限界を勝手に決めるな」という強いメッセージがありました。自分でそう思った時点でそれ以上はいけないからです。
オシム氏はとにかくよく見ており、ピッチ内だけでなく、リハビリをしている選手の様子やスタッフの振る舞いまで、すべて観察していました。この絶え間ない観察と洞察力が、チーム全体のレベルを引き上げていったのです。

日本人選手の特性と新しいものを創造する力
オシム氏は、トレーニングで複数の選択肢を提示された場合、日本人選手は提示されたこと以上のもの、例えば新しいものをクリエートしたりといったことをしない傾向があると指摘しました。
東洋大学の監督は、日本人は提示されたものの中でやるのは得意だが、その意味や次のレベルの思考は苦手な分野かもしれないと同意しています。これは「小さな器の中でやらされてきていること」が大きいのではないかと分析しています。
この指摘は、サッカーだけでなく、日本の教育やビジネスの現場にも通じる重要な視点です。与えられた枠組みの中で最善を尽くすことは得意でも、その枠組み自体を疑い、新しい可能性を切り開く力を育てることが、今後の日本に求められているのかもしれません。
東洋大学での指導哲学と選手との向き合い方
ジェフでのコーチの経験後、監督はシンガポールのアンダーカテゴリーの監督を務めました。東南アジアは初めての経験で、マレー系、中華系、インド系、ヨーロッパ系など様々なルーツの人々がおり、公用語が英語であるなど、日本の常識が世界では常識ではなくなることを実感しました。
現在の東洋大学では、監督は毎日全員の顔が見えて言葉を交わせる人数を重視しており、何より選手が「東洋大学に来たい」「ここでプレイしたい」と思っていることが重要だと考えています。無理やり連れてきてもプラスにはならないという哲学を持っています。
今回紹介した対談は前編のみの内容です。実際の動画では、さらに深い指導論や、全国大会優勝に至るまでの具体的な戦略、そして後編ではより実践的な内容が語られています。オシム氏の教えがどのように東洋大学の強さに結びついているのか、現代の大学サッカーが果たすべき役割とは何か。
日本一の監督が語る指導の真髄が、あなたのチームづくりや人材育成のヒントになるはずです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



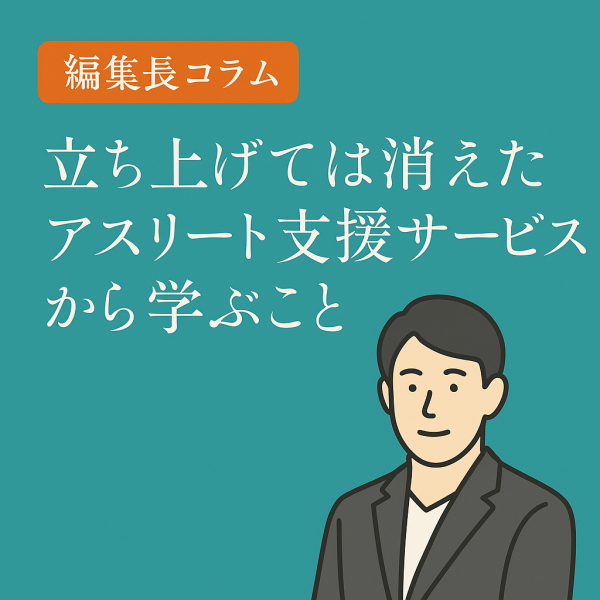
の勘定科目-600x450.png)











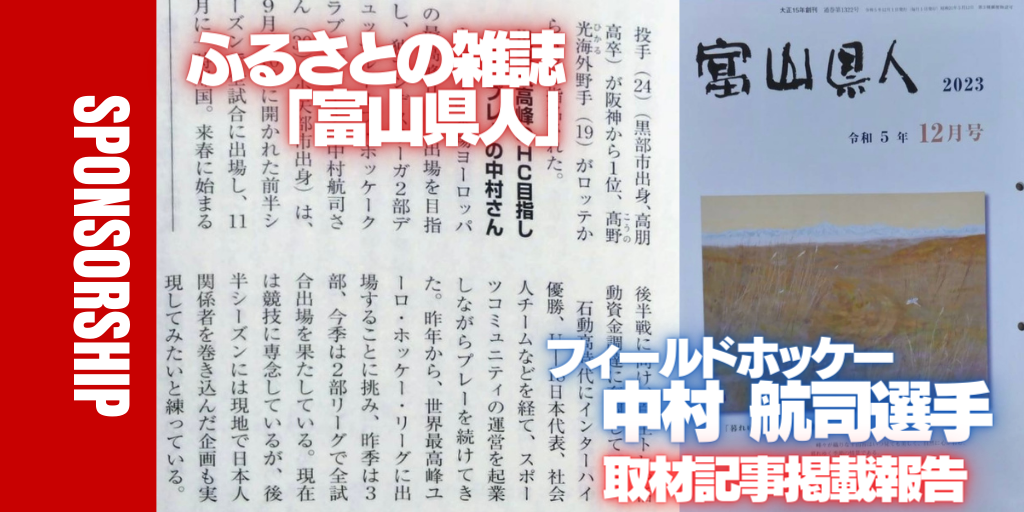



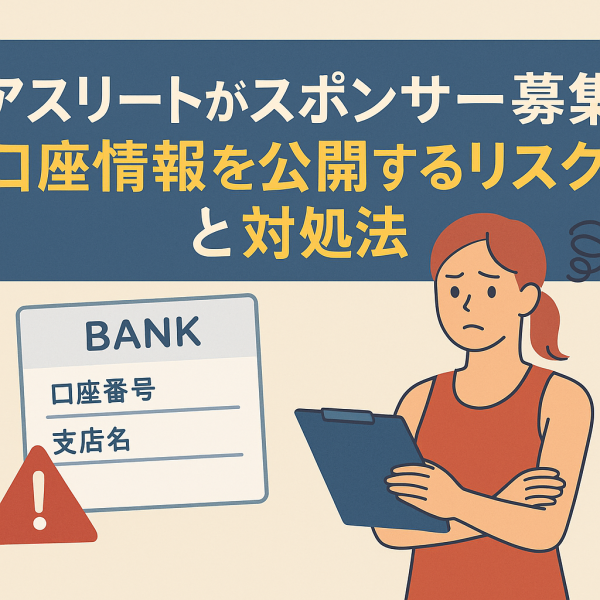









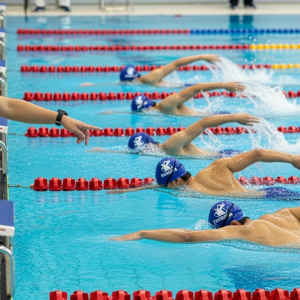



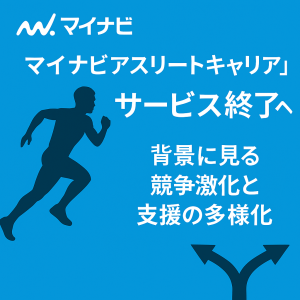


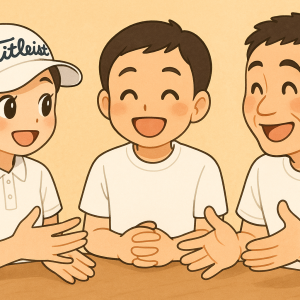
この記事へのコメントはありません。